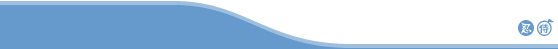「一年を終えると、あたかも冬こそすべてであったように思われる。土が残雪であり、水が残雪であり、草が残雪であり、さらには光までが残雪の余韻だった。春があっても、夏があっても、そこには絶えず冬の胞子がひそんでいて、この裏日本特有の香気を年中重く澱ませていた。」
宮本輝の『蛍川』の一節。
寄寓人も富山に初めてやってきた頃は、その重く澱んだ香気を受けとめていたような気がする。たんこさんと暮らし、お山に寄寓し、螢川の舞台となったいたち川の畔に住むようになって、少し変わった。
いたち川の春の桜は、長い冬の終わりを満面の笑みで祝う。そして、お山では山が嗤う。
長い冬だからこそ、待ち遠しくて、啓蟄を祝い、桜を愛で、山の嗤いにつられて笑う。富山のよさだよね。山ほんとに嗤うんですよ。ほんとに。大長谷ではいま山が嗤っています。


 [1回]
[1回]
PR